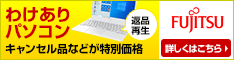|
|---|
| 辣椒氏の風刺画。パソコン、エアコン、スマホ、珈琲、スーツと現代生活を楽しむ中国人。しかし、その辮髪が示す通り、意識はまだ近代化されていない |
中国でのネット規制はますます厳しい。特に習近平体制以降厳しくなったとは、母国と同様にネットを活用したい中国在住の外国人は、ひしひしと感じるところ。
中国側のアクセス遮断に対抗するには、VPNの利用が定番の方法だが、そのVPNも繋がりにくくなりストレスがたまる。
また、アクセスできる海外サイトについても、企業は「料金を払えば一時的に高速で海外サイトにアクセスできる」オプションをさりげなく用意し、デフォルトで回線速度が遅くなっている。
習近平体制以降の新たなネット規制を挙げると、「Googleのサービスが完全にシャットアウト」「Appleの中国ユーザーについてサーバーの中国移転」「LINEが一時的に利用不可になる」などがある。
その一方で「北京で開催のAPECで、会場限定で規制を完全に撤廃し、海外のVIP向けに時限的にインターネットを開放」するなど、新たな技を身につけ、披露している。
中国人にも数多くのネット対策を行なった。ほんの一例をあげれば「フォロワーが多く、発言に影響力があるオピニオンリーダーや、IT企業に対して、ネット道徳遵守を約束」させ、「RT500回でデマを流した罪で懲役と最高裁が通達」し、「オピニオンリーダーを拘束」したことが挙げられる。上の動画は、中国政府が用意した中国市民に優しい政治をわかりやすく解説するコンテンツだ。
そしてこの習近平体制で、特に中国人向けのネット世論対策がブラッシュアップされた結果、就任当時は「ネットで革命が起きるのではないか」と言われていたほどの人民のネットの力がそぎ落とされた。これは中国在住の外国人も、平時からアンテナを立ててないと気付かないほどに、さりげなく行なわれてきた。
加えて、SNSの主流が、不特定多数に拡散されるTwitter型の「微博(Weibo)」から、拡散しずらい閉じたLINEのようなメッセンジャー「微信(WeChat)」への人気の移行や、政府擁護のコメントをネットに書き込む「五毛党」の存在、書き込みが削除されても書いた本人には気づかれないような新検閲システム、「ビッグデータを活用したネット世論警報システム」が開発され、ますます反中国的な書き込みが世論の渦となることが難しくなっている。
中国の巧妙なネット世論誘導手法を
解説する本が登場
 |
|---|
| 高口康太氏著「なぜ、習近平は激怒したのか」(祥伝社新書) |
これを解説した本が、最近出版された高口康太氏の著書「なぜ、習近平は激怒したのか――人気漫画家が亡命した理由」だ。この人気漫画家とは、風刺画を描く「辣椒(ラージャオ)」氏のことで、現在も亡命した日本で中国の風刺画を描いているが、この本の多くが「中国の最大の敵」たるネット世論をいかに巧妙にコントロールしたかというところに割かれている。
本書に書かれている中国のその巧妙なるネット世論誘導手法を紹介すると、「政府サイドが、習近平ファンの一般市民を自称するアカウント“学習ファン団”を作成し、大手メディアよりも早く情報を伝え、習近平氏の写真を至近距離から撮影。一般市民目線をアピールすることで、さりげなく多くの一般人フォロワーを獲得した」「真実味があると思われる香港メディアを活用して習近平のいい人エピソードを発信」「人民解放軍や警察が大規模や予算を投入し、本気を出してハイクオリティな“踊ってみた”コンテンツをアップ」「政府御用ブロガー・政府御用ネット小説家・政府御用漫画家を誕生させる」などといったもの。
高口氏は「習近平体制は、お堅いはずの中国共産党が、ネット論壇の手法を模索し、ポップな手法を駆使した国民の支持獲得にまい進している」という。
それでも大事故や大事件が起きれば、中国政府の責任が問われることもある。本書では野次馬の力に注目している。ネットで拡散し、注目を集めるだけ集めれば、政府サイドは後に引きにくくなるということだが、そのネットの野次馬パワーがいかんなく発揮されたのが、(細かくは書かないが)「中国ジャスミン革命」であり「高速鉄道脱線事故」で、政府を動かすことに成功した。
その野次馬対策では、前述の「微博から微信へのシフト」「世論誘導の五毛党」「新検閲技術の開発」が挙げられるが、それでも完璧ではなく、野次馬は集まる。
そこで政府は、問題が起きたら「当局が責任者の処罰、徹底的な救助姿勢を見せるなど、ネット世論を意識しさっさと幕引きをはかる姿勢」を見せ、ツケ払いを宣言をし、新たなネタを投入し、野次馬の気をそのニュースから別の話題に逸らすという手段をとる。時間が野次馬の関心をそらした後は、当局は弾圧や処罰などの手段がとれるわけだ。
その結果、もともとはネットでバズるのは政府批判ばかりだったが、今では政府のコントロールがかなり聞くようになり、400人以上が死亡した長江客船沈没事故や天津爆発事故でもあっという間に話題が沈静化するようになった。「当局の力がかなり効いている状況」だと高口氏は分析する。
「そもそも中国のネットの動員力に、外野の外国人・外国メディアは、中国のリアルよりも過剰に期待をし、当の中国当局までもリアルよりも過剰に恐れていたのではないか」「ネットユーザーが増えたことにより、関心は内輪になり、それ以外に無関心になった」と高口氏は指摘。
辣椒氏は「中国の詰め込み教育のせいで、創造力どころか、自律性、つまり“自分の頭で考える”ことが欠乏している人だらけではないか」と指摘している。つまり、ネットにおいても、中世から変わらぬ「慈悲深い支配者と救われる愚民」の関係から変わっていない、というわけだ。
(次ページに続く、「「なぜ、習近平は激怒したのか」の著者にインタビュー」)
この連載の記事
- 第107回 中国の匠が作るマインクラフトの世界がスゴイ!
- 第106回 天津大爆発の情報の少なさに見る、中国のネット規制の現実
- 第105回 一見ガラケーだがフタを開くとスマホに変身! 中国の老人向けスマホがスゴイ!!
- 第104回 話題の安倍首相ロボも! 中国のロボット展示会で最新中華ロボを体験!!
- 第103回 AppleWatch発売に乗じて……中国の変わり種スマートウォッチあれこれ
- 第102回 SNSで操作するエアコンやおむつセンサー……中国で増えているスマート家電
- 第101回 中国で4~6画面のマルチディスプレーPCがバカ売れしている理由
- 第100回 Wiiっぽいゲーム機に進化版!? 中国老舗メーカーの7000円学習パソコンを試す!
- 第99回 ガワがニセモノ!? 中国で売られている安いiPhoneの落とし穴
- 第98回 「キャンディークラッシュ」もどきアプリに中国式モノ作りを見た!
- この連載の一覧へ


























_60x60.jpg)